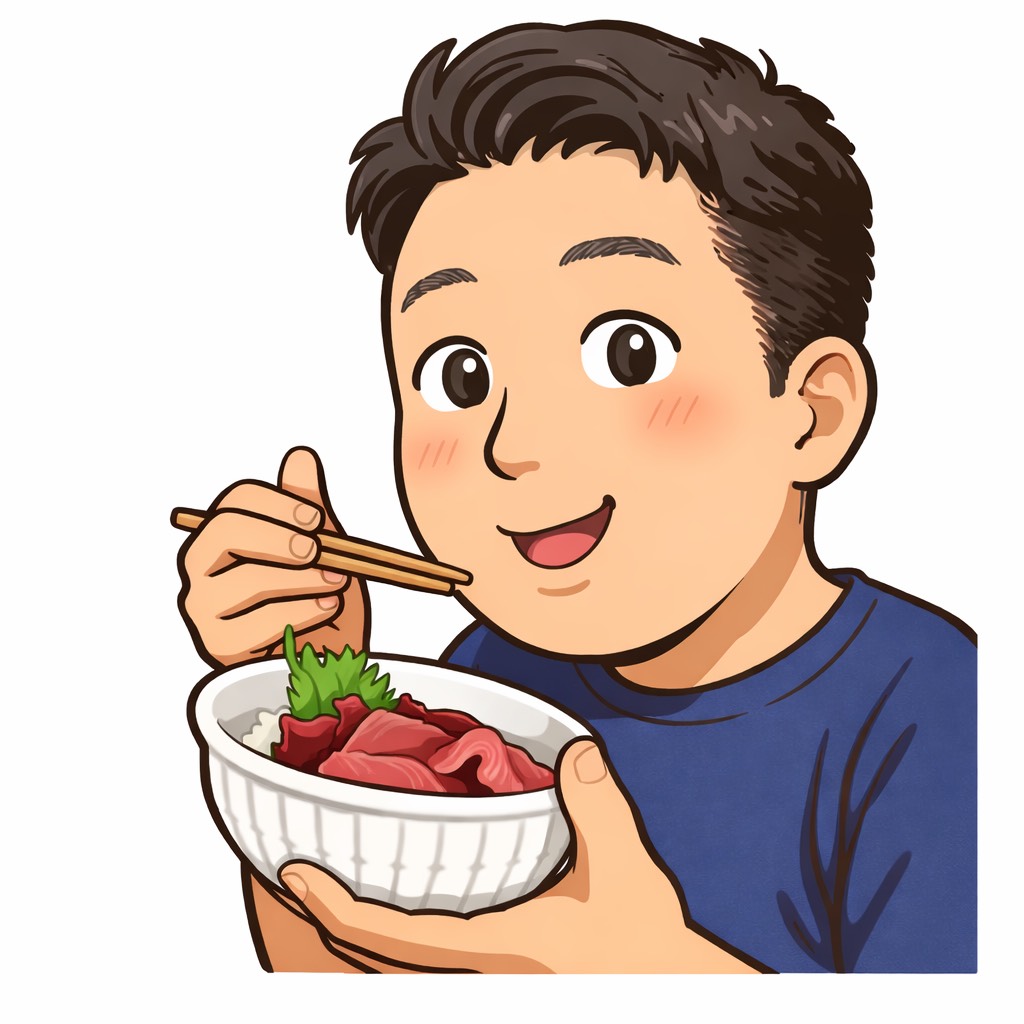【大豆】未来への希望を託す、奇跡のスーパーフード
「大豆って、豆腐とか納豆とか、昔ながらの食材のイメージしかないよね?」
そう思ったあなたへ。
どうもチーパパです。
実は大豆は、私たちの健康を支え、環境問題解決の鍵を握る、
「奇跡のスーパーフード」!!
今回はそんな大豆について。
この記事では大豆についてと、
初心者でも、生育ステージ、栽培方法などのイメージつかめるようになっています。
大豆の基本情報
栽培の歴史
私も母から「大豆は体に良いの食べなさい」
と言われてきましたが、調べてみるとびっくり、
大豆は紀元前3000年頃から中国で栽培が始まり、
5000年以上もの歴史を持つ、
人類にとって最も古くから親しまれてきた作物の一つ。。
すごいな大豆、ナメてました。
大豆の栄養価と食育
大豆の栄養を調べてみると、、、
- タンパク質: 大豆100g中には約35gのタンパク質が含まれており、これは牛肉や豚肉と同等の量、しかも、大豆タンパク質は必須アミノ酸をバランス良く含むため、動物性タンパク質に劣らず、質の高いタンパク質として評価されてる。
- 食物繊維: 大豆には、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方が含まれており、腸内環境を整え、便秘解消やコレステロール値の抑制に役立つ。
- イソフラボン: 大豆に含まれるイソフラボンは、女性ホルモンと似た働きをする成分で、更年期障害の改善や骨粗鬆症予防、美肌効果などが期待されていて、大豆イソフラボン含有量は、100gあたり約30mg。
- サポニン: 大豆サポニンは、血糖値の上昇を抑え、コレステロール値を下げる効果が期待されている。
大豆は高タンパク質で栄養価が高く、ダイエットや健康維持に役立つ!
枝豆とか、最近は蒸した豆商品などがスーパーに並んでいるので、
我が家の食卓にも登場するのだが、子どもから大人気。
引き続き食べさせるか。
栽培は?
栽培の観点から。
大豆は、イネ、ムギ、トウモロコシなどの穀物に比べて、やせ地でもよく育つ植物で、
肥料などは少量で済む作物です。
実際プロ農家でも、特に窒素はほどんど施肥していない。
畑によってではあるが、大豆の根に根粒菌がつくまでの初期に窒素を施す程度、
もともとは、他の作物より窒素を多く吸収する特性があるが、根粒菌と共生することで土壌の栄養を効率的に利用でき、人間が施す窒素肥料はごくわずか。
大豆の栽培方法
大豆は手間がかからない作物と言われています。
実際プロ方も、
「面積が多くなりすぎて、手が回らないから大豆の栽培をするわぁ」
などが多いです。
実際に、播種時期が他の作物と違う事や、
防除の回数も少ないなどのメリットがあります。
栽培の基本ステップ
大体のイメージはコレ!
大豆の種まきは4月から5月に行い、9月から10月に収穫する。
株間は10−20cm、畝間は60−70cmを目安にする。
土寄せを2−3回行うことで、根の成長を促進し、倒れづらくする。
大豆の生育過程
大豆の種が土から出て、子葉が開くと成長が始まる。
中耕を行うことで土に空気を入れ、地温を高め、窒素の吸収を促進する。
雑草が生えてくる時期は、種まきから約1ヶ月後から。
(畑を耕しているので、すぐには雑草は生えてこない)
生育時期の重要性
子葉が出てから初生葉が出るまでの間は、種の栄養で生育するため、この期間の管理が重要である。初生葉を失っても、再び初生葉が出てくれば生育は続くが、早期の管理が求められる。
大豆の受粉と生育
受粉のメカニズム
大豆の花は午前中に開き、受粉が行われる。
1株に約100個の花が咲くが、そのうち実になるのは20−30個程度で、
枝豆として食べる場合は、花が咲いてから約1ヶ月後に収穫する。
枝豆で食べる方が多いかな?
葉の成長と役割
大豆の葉は子葉、初生葉、本葉に分かれ、それぞれの成長段階で異なる役割を果たす。
本葉は互いに出てくるが、初生葉の縁まで成長することで、植物全体の成長を支える。
葉枕は筋肉のような役割を果たし、莢も光合成を行う。
大豆と根粒菌の関係
根粒菌の役割
根粒菌は空気中の窒素を養分として利用し、大豆にとって重要な共生関係を築く。
植えてから約2週間で根粒菌が根に付着し、窒素を植物が吸収できる形に変化させる。
過去に大豆を栽培していない圃場では根粒菌が少ないため、菌を降る必要がある。
栽培後(2〜3週間後)に根を見て、
10個くらい根粒菌(根に丸い白い粒)が付いていたら生育順調!
土壌の栄養の役割
大豆を栽培した後、土壌には窒素が残るため、次の作物にとっても有益である。
だが、莢などは分解がされずらく、逆に土壌に分解に窒素を使ってしまう事もある。
大豆の病害虫管理
主な害虫と対策
大規模栽培の場合(プロ)
タネバエは芽が出る前の種を食べるため、早期の対策が必要であり、
最近は専用の農薬などを種に塗布してから播種する。
コレをやることで約1ヶ月の間の殺虫効果や殺菌効果が期待できる。
生育途中としては、カメムシ、ハスモンヨトウなどが、
枝豆の時期に汁を吸う害虫として知られている。
アブラムシも生育時期に影響を与えるため、注意が必要である。
まとめ
今回の記事はいかがでしたか?
大豆の栽培は、手間ひまかけてこそ美味しい枝豆が待っています。
皆様の畑でも、愛情込めて育てた大豆が、
最高の収穫をもたらしてくれることを期待致します。
ぜひ、次回の記事も楽しみにしていてくださいね!
あなたの栽培を応援しています!