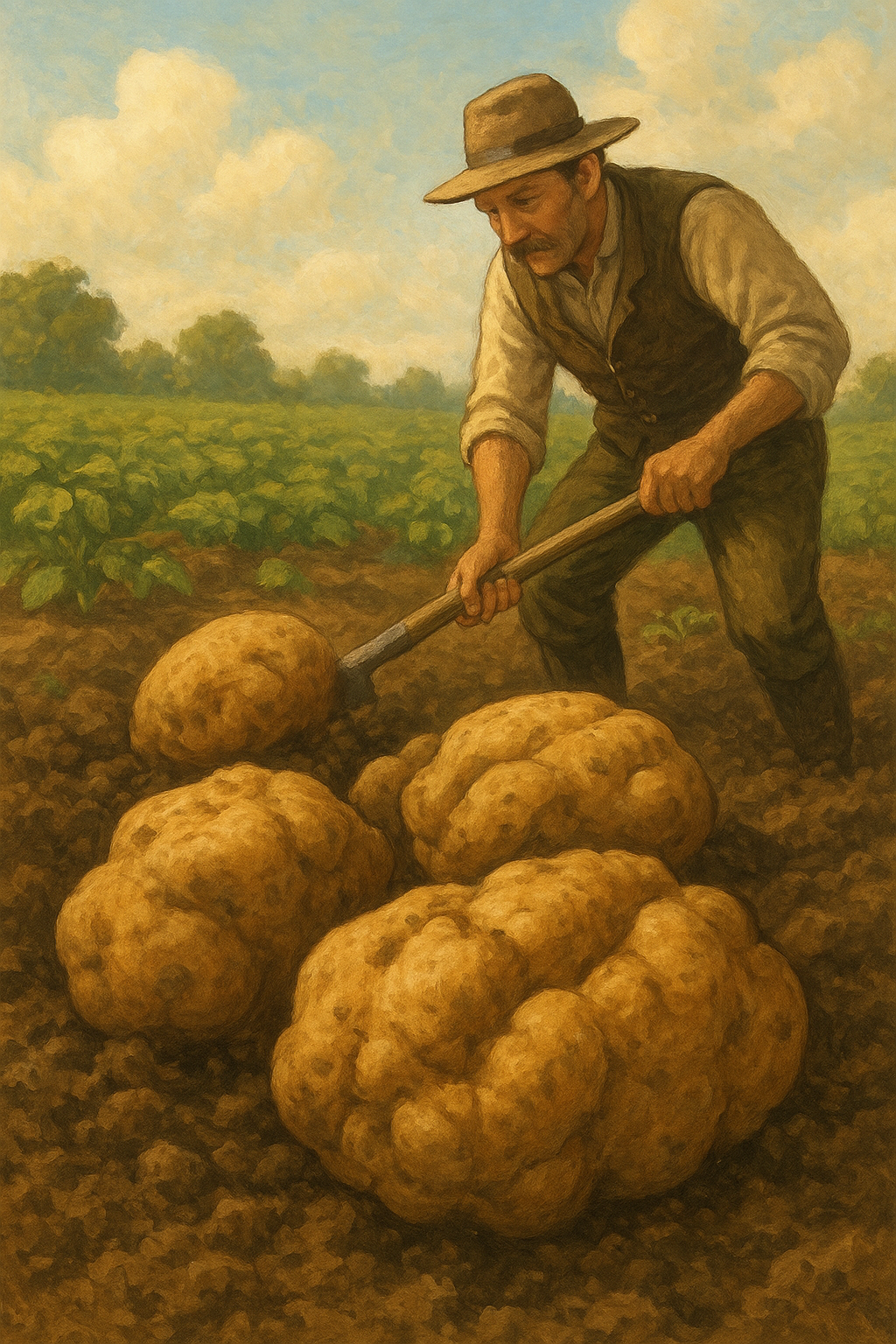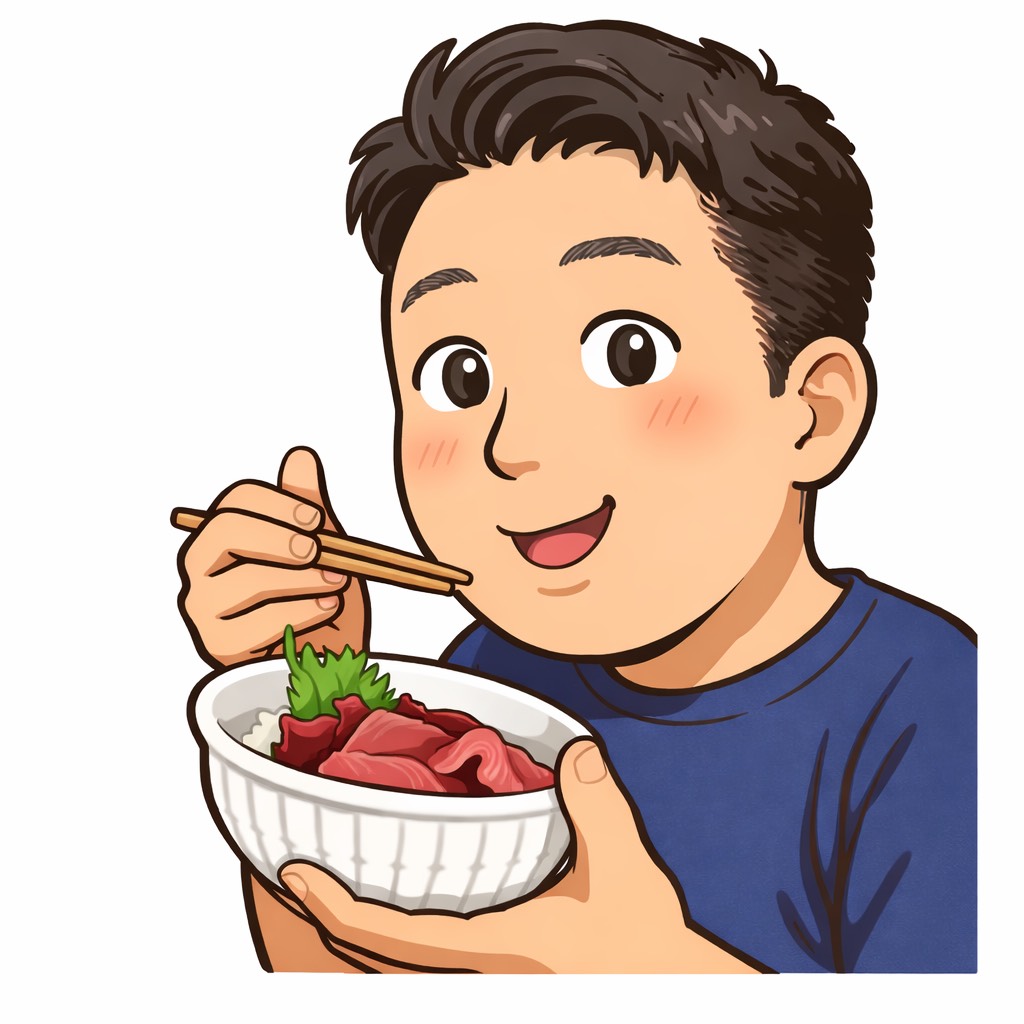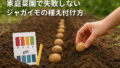今年の失敗から学ぶ、来年に活かせるジャガイモづくりのヒント
皆さんこんにちはチーパパです。
皆様イモの収穫終えましたか?
土をほってみると衝撃的なイモ多くなかったですか?
今回の記事は、今年の反省を活かし、来年に向けた対策内容となっております。
1.今年の収穫を振り返って
今年も無事?に男爵薯の収穫を終えました。
ただ、今年は例年に比べて特徴的なことがありました。
- 高温・干ばつの夏 → 生育後半に雨が続いた
- 2次成長したイモが多発
- そうか病の発生も目立つ
味自体は変わらず美味しいのですが、見た目に大きな影響が出ました。特に2次成長のイモは、形がゴツゴツしてしまい、厳しい仕上がりに…。

2.「2次成長」とは?そのメカニズム
今年のように干ばつの後に雨が続くと、芋が再び成長を始めることがあります。
これを「2次成長」と呼びます。
- 一度成長が止まったイモが、再び肥大を開始
- 表皮が割れたり、段差ができたり、ゴツゴツした形に
- 主に水分条件の急変が原因
つまり、水分の安定供給ができなかった年に起こりやすい現象です。
3.「そうか病」とは?そのメカニズム
もう一つ、今年目立ったのがそうか病です。
- 病原菌:Streptomyces scabies(放線菌)
- 特徴:イモの表面にかさぶたのような病斑ができる
- 発生条件:
- 土壌が乾燥 → 発生しやすい
- pHが高め(中性~アルカリ性) → 発生が助長される
つまり、今年の干ばつと土壌条件が重なって発生が増えたと考えられます。
4.対策方法(家庭菜園・農家向け)
◆ 2次成長の対策
- 土壌水分を一定に保つ(マルチ、かん水管理)
- 極端な干ばつ後の過剰なかん水を避ける
- 品種選び(2次成長しにくい品種を選ぶ)
◆ そうか病の対策
- pHを下げる(酸性資材:硫黄粉、硫酸アルミニウムなど)
- 有機物のすき込みで土壌環境を改善
- 輪作を徹底し、連作を避ける
- 種イモの消毒を徹底
5.まとめ
今年のジャガイモは、
- 高温干ばつの後の降雨で2次成長が多発
- 土壌条件と干ばつでそうか病が多発
という厳しい結果になりました。

ほとんど、こんなのばっかり。
ただし、味は例年通り美味しい!
形や見た目に課題は残りましたが、家庭で食べる分には十分楽しめそうです。
来年は水分管理や土壌改良を徹底し、より良い男爵薯を目指していきたいと思います。
みんなで美味しい作物を作りましょう!