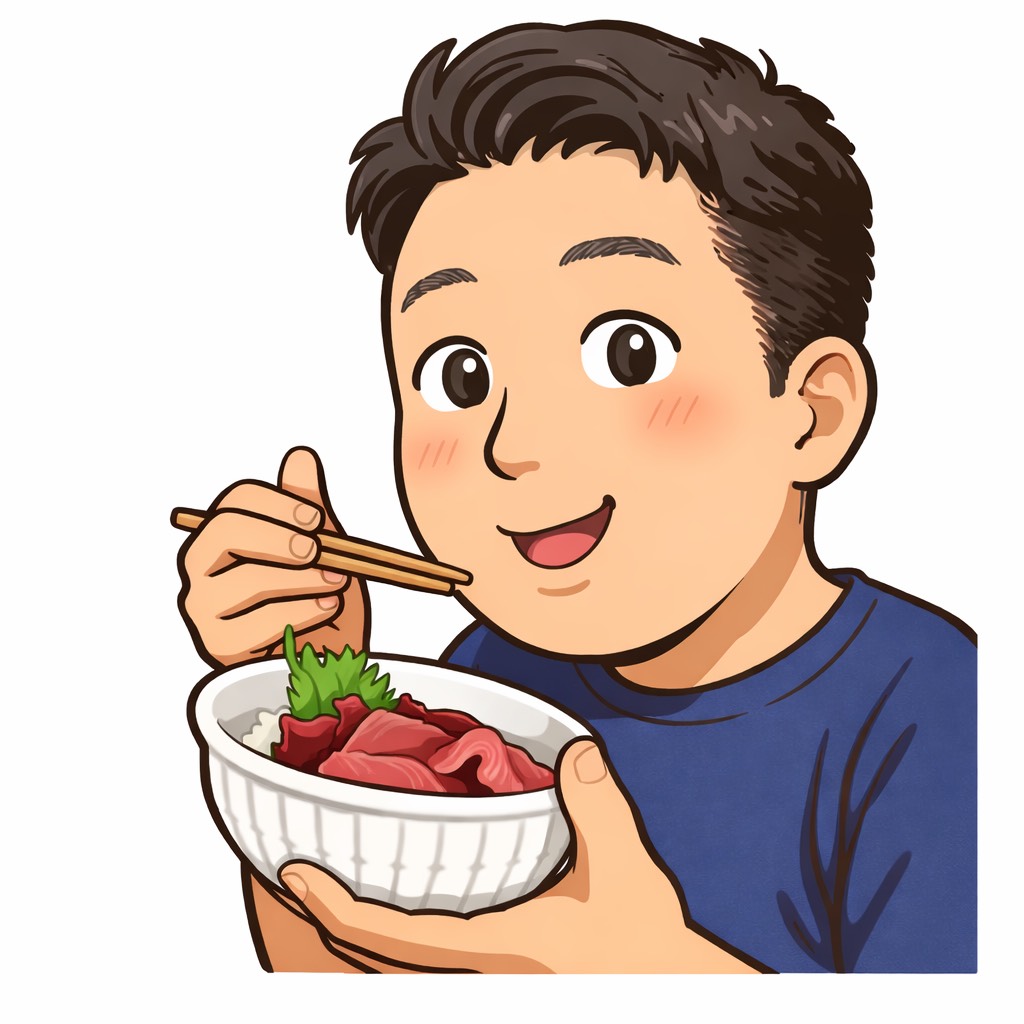【害虫比較】シロオビノメイガ・ヨトウガ・シロイチモジヨトウの違いと防除のヒント
どうもチーパパです。
近年暑いせいか、害虫と雑草の対策が激ムズですよね。
今回は最近北海道で話題になっているシロイチモジヨトウと既存の害虫について!
ネギや葉菜類を育てると必ず出てくるのが「ヨトウムシ類」や「メイガ類」と呼ばれる害虫たち。
ここでは シロオビノメイガ、ヨトウガ、シロイチモジヨトウ の3種を比較し、それぞれの特徴や防除のコツを整理しました。
1.シロオビノメイガ(Hymenia recurvalis)
特徴と被害
- 葉をすりガラス状に食害し、成長すると葉を綴り合わせて中で食べる。
- 激発すると葉が丸坊主に。
- 夏~秋に多発、特に9~10月がピーク。
防除ポイント
- 雑草(アカザ類、イヌビユなど)や放置圃場を除去。
- 防虫ネットで侵入防止。
- 登録農薬がないため、ヨトウ類と同時防除が基本。
2.ヨトウガ(Mamestra brassicae)
特徴と被害
- 卵を数十~数百粒まとめて産卵。
- 若齢期は葉裏で群生、4齢以降は夜間に暴食。
- 激発時は葉脈だけ残り、圃場全体を食べ尽くすことも
。 - 年2回発生(6~7月、8~9月)。
防除ポイント
- 卵塊の調査が重要。50株に2卵塊以上で防除開始。
- 若齢幼虫期を狙って薬剤散布。
- 秋耕で地中の蛹を破壊。
3.シロイチモジヨトウ(Spodoptera exigua)
特徴
- 別名「テンサイヨトウ」。英名 Beet armyworm。
- 前翅は灰褐~黄褐色の地味な小型の蛾。
- 幼虫は淡緑~緑褐色で、白~黄色の背線が数条。
被害の出方
- ネギ圃場では7月から発生、8~9月にピーク。11月まで被害が続く。
- 卵は10~数十粒の卵塊で産みつけられ、尾毛で覆われるのが特徴。
- 幼虫は3齢までは葉の中に食入し葉肉だけを食害 → 白い表皮だけ残り折れる。
- 4齢以降は分散して外側から葉を食害。坪状の被害が出やすい。
- 虫糞が葉の中にたまり、根深ネギでは収穫時の洗浄に大きな労力がかかる。
発生の特徴
- 広食性でネギだけでなくエンドウ、スイカ、ダイコン、花卉類も加害。
- 年間5~6回発生、耐寒性も強く露地で越冬可能。
- 薬剤抵抗性が強く、国外から飛来する可能性もある。
防除のポイント
- 若齢期に防除することが最重要。齢が進むと薬効が落ちる。
- 同一薬剤を連用すると抵抗性がつきやすい → 薬剤ローテーション必須。
- フェロモン剤(ヨトウコン-S、コンフューザーV)で交尾阻害。
- 飛込み防止ネットや**黄色蛍光灯(忌避効果あり)**を補助的に活用。
- ネギで 株当たり1頭以上の中齢幼虫が見つかると減収リスク大 → 散布の目安。
4.違いをまとめると…

| 項目 | シロオビノメイガ | ヨトウガ | シロイチモジヨトウ |
|---|---|---|---|
| 分類 | メイガ科 | ヤガ科 | ヤガ科 |
| 発生ピーク | 9~10月 | 6~7月・8~9月 | 8~9月(被害は11月まで) |
| 被害の特徴 | 葉裏 → 葉を綴る → 丸坊主 | 若齢期は群生 → 夜盗化し暴食 | 葉に食入 → 白化 → 糞がたまり品質低下 |
| 寄主作物 | 葉菜類全般 | キャベツ・ハクサイ等アブラナ科 | ネギ中心(他に多数の野菜・花卉) |
| 越冬 | 不明確(暖地性) | 蛹で越冬 | 幼虫・蛹で越冬(耐寒性あり) |
| 登録薬剤 | なし(同時防除) | 多数あり | 抵抗性が強く難防除、フェロモン剤あり |
| 防除の要点 | 初期発見・雑草除去 | 卵塊調査・若齢期防除 | 若齢期に防除、薬剤ローテーション、物理的防除も活用 |
まとめ
- シロオビノメイガ → 秋に増える。登録薬剤なし、雑草除去と同時防除がカギ。
- ヨトウガ → 年2回発生。卵塊調査と若齢期防除が勝負。
- シロイチモジヨトウ → ネギ害虫の代表格。抵抗性が強く、若齢期以外は効きにくい。フェロモン剤や物理的防除と組み合わせて対策を。
👉 共通点は「早期発見と若齢期防除が必須」ということ。
日々の見回りと発生予察を組み合わせて、被害を最小限に抑えましょう。
ちなみにシロイチモジヨトウのおすすめ農薬はディアナ!
|
|
やっかいな害虫を防いで、
美味しい作物を作って食べましょう!!
参考文献
・新・北海道病害虫ガイドブック。
・北海道病害虫防除所

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4acc508a.3fdd2851.4acc508b.3222fb8d/?me_id=1398639&item_id=10000623&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsandounouen%2Fcabinet%2Fimgrc0092345180.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)