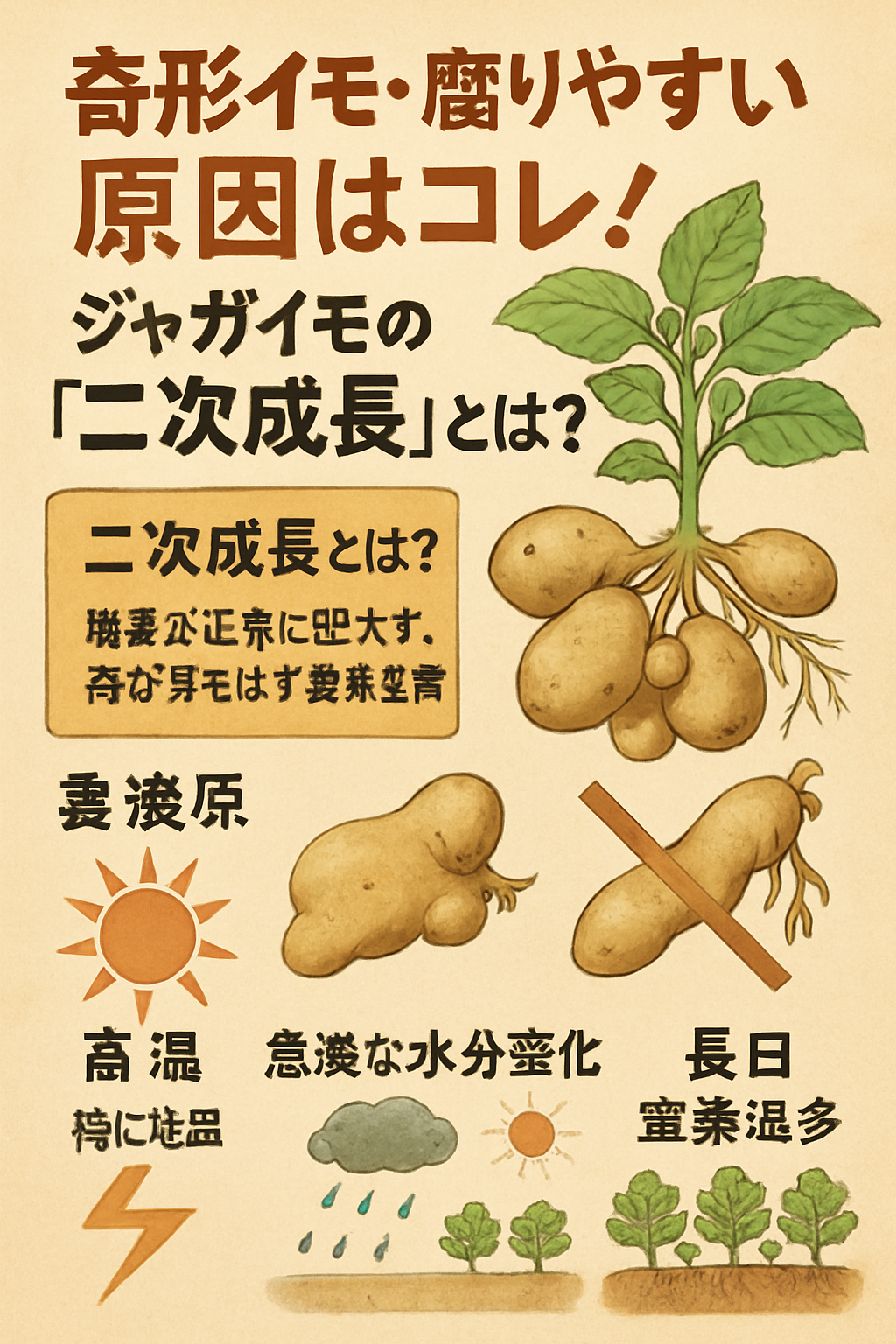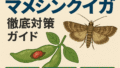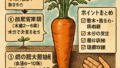【奇形イモ・腐りやすい原因はコレ!】ジャガイモの「二次生長」とは?塊茎形成の仕組みと防ぐ方法【保存版】
🥔「ジャガイモがヘンな形に…」その原因、二次生長かもしれません!
ジャガイモを育てていると、
- 「ひょうたん型のイモができた…」
- 「収穫したら芽が出てる!?」
- 「保存してもすぐ腐る…」
こんな経験、ありませんか?
どうもチーパパです。
その正体は「二次生長」。(動物は成長、植物は生長、、、)
塊茎が正常に肥大せず、再び芽を出すなどの異常生育で、品質・収量に大きく影響します。
この記事では、プロ農家も家庭菜園も知っておきたい、
✅ 塊茎形成のメカニズム
✅ 二次生長の原因と症状
✅ 失敗を防ぐための実践対策
を徹底解説します!
🧠 ジャガイモの「塊茎」ができる仕組みを知ろう!
まずは基本となる「塊茎形成」の条件から。
これを押さえておくことで、異常の早期発見と予防が可能になります。
① 日長(昼の長さ)が重要!
| 日長条件 | 塊茎への影響 |
|---|---|
| 短日(12時間以下) | 塊茎形成が早く進む |
| 長日(16時間前後) | ストロン(地下茎)が伸び、塊茎形成が遅れる☞ そのぶん葉が茂り、光合成が活発→収量増も期待 |
🌟【ポイント】長日だから悪いとは限らない!
光合成量を活かせる環境なら最終収量UPも。
② 温度もカギ!理想は「やや涼しめ」
| 温度条件 | 影響 |
|---|---|
| 20℃以下 | 最も塊茎がよく育つ |
| 30℃以上 | 塊茎形成はほぼ停止。葉や茎ばかり育つ |
| 夜温が低い(10~23℃) | 栄養が塊茎に集中。高温でもイモがつく |
🌡️【注意】日中が高温でも、夜間が涼しければ問題なし!
北海道など高緯度地域の夏栽培にピッタリの理由です。
(最近はものすごく暑そうですけど、、、)
③ 日長×温度の「組み合わせ」で決まる
| 条件 | 効果 |
|---|---|
| 短日 × 夜温23℃以下 | 日中30℃でも塊茎形成OK |
| 長日 × 昼17℃ × 夜10℃ | 最も塊茎が多く形成されやすい |
⚠️ 要注意!これが「二次生長」だ!
二次生長とは?
一度肥大を始めたイモが、再び成長・発芽してしまう異常生育。
「二次生長」「異常塊茎」とも呼ばれます。
【主な症状】
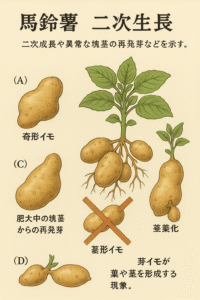
※イメージ
| 現象 | 内容 | 問題点 |
|---|---|---|
| 🔄 奇形イモ | ひょうたん型・細長い・芽が出る | 見た目が悪く、でんぷん価が低下 |
| 🌱 孫イモ発生 | 肥大中のイモが再び芽を出す | 養分が分散して収量ダウン |
| 🌿 茎葉化 | イモの先から葉や茎が出てくる | デンプンが使われ保存性低下 |
😨これらは、食味・保存性・収量・種イモとしての価値すべてに悪影響!
🔥 二次生長の原因を突き止めろ!
| 主因 | 詳細 |
|---|---|
| 🔥 高温(特に地温) | 芽の休眠が破れて再発芽。昼間の強烈な暑さに注意 |
| 💦 急激な水分変化 | 大雨やかん水による急変でイモが混乱 |
| ☀️ 長日条件 | 茎葉が過剰に伸び、イモへの養分移行が乱れる |
| 🧪 窒素過多 | 葉ばかり茂ってイモが育ちにくくなる |
✅ 今すぐできる「二次生長」対策
対策1|地温を下げる
- 培土でイモに直射日光を防ぐ(コレは皆様だいたいやっている、、、)
- 暑い日はかん水(朝か夕方)で土を冷やす
対策2|肥料は控えめに!
- 元肥中心にして、追肥は最小限に(特に生食、加工イモ?)
- 特に窒素分のやりすぎ厳禁
対策3|水分管理を安定させる
- 過湿・乾燥の繰り返しを避ける
- マルチ栽培で地温・湿度を安定させるのも効果的
対策4|品種と時期を見直す
- 二次生長が起きにくい品種を選ぶ
- 高温期の栽培を避ける
📝 まとめ|環境管理がジャガイモ成功のカギ!
| 良い環境 | 二次生長を防ぐコツ |
|---|---|
| 短日×低温 | 塊茎が早く・安定して形成される |
| 高温×長日×窒素過多 | 二次生長が発生しやすく品質ダウン |
地温管理・水やり・肥料の調整をしっかり行えば、
二次生長を防いで、形の良いおいしいジャガイモが育ちます!
🎯この記事はこんな方におすすめ!
- ジャガイモ栽培で奇形や発芽に困っている方
- 収穫量や保存性を改善したい農家・園芸愛好家
- 二次生長を根本から防ぎたい方
📚参考文献
- 『農業技術大系』作物編 第5巻
第四章 塊茎の形成と生理的障害
農業はコントロールが出来ないこ事が多く大変ですよね。。
自身でコントロールできる事をコツコツやっていきましょう!