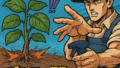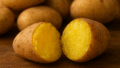シロオビノメイガの発生と防除方法
畑を歩くとフワァ〜っと舞う害虫。。なんかいますよねぇ。
こんにちは、チーパパです。
今回はシロオビノメイガ、
名前の通りに羽に白い帯が見えて、
チョロチョロしているからチョットイヤ。
そんなシロオビノメイガ Spoladea recurvalis は、テンサイ・ホウレンソウ・ウリ類などを加害する害虫です。特に秋季に発生が多くなり、放置すると葉が丸坊主になるほどの被害を及ぼします。今回はその特徴や発生経過、防除のポイントについてまとめます。
幼虫の特徴と食害の様子
-
幼虫の体長:老熟すると約15~20mm
-
体色:淡い緑色~淡黄赤色、やや透明感がある
-
頭部:淡黄褐色に褐色の斑点が点在
-
行動:尺取り虫のように歩き、驚くと脚を縮めて後退し、最後には葉から落下する
食害の特徴

-
幼齢期は葉の表皮を残して葉肉を食べるため「網目状」の痕跡が残る
-
成長すると葉を糸で綴り合わせ、その中で食害
-
多発すると葉に不規則な穴があき、やがて葉全体が食い荒らされ、葉柄だけが残る被害になる


ヨトウほどガツガツ食べなくて、
網目状や、小さな穴が開くってよく聞きますね。
発生の経過と生活史
-
卵:雌成虫は1株に80~100粒を産卵。葉裏の葉脈沿いに並べる
-
卵→成虫までの発育期間:25℃で約24日
-
幼虫期:12日前後で老熟し、地中や落葉の間で蛹化
-
蛹期:約2週間
-
発生回数:年3回(北海道報告)~5~7回(本州以南の暖地)
-
発生ピーク:7月以降増加し、9月~10月に最も多い
-
越冬形態:蛹で越冬すると考えられているが、成虫の長距離移動も疑われている
成虫の特徴

-
開帳:20~24mm
-
翅:暗褐色で中央に目立つ白帯。後翅にも白帯がある
-
外見:前翅の中央にある白い帯模様が識別ポイント
発生しやすい条件
-
秋に気温が高く、雨が少ない年に多発しやすい
-
雑草(アカザ、シロザ、イヌビユなど)や近隣の寄主植物で増殖する
-
施設栽培や雨よけ栽培では被害が拡大しやすい
防除のポイント
耕種的防除
-
圃場周辺の雑草(アカザ、シロザなど)を早期に除去する
-
施設栽培では、防虫ネット(目合い4~5mm)を張り、成虫の侵入を防ぐ
-
初期は局地的発生が多いため、被害株を早期発見し局所防除が有効
現場での実践的な防除プログラム例
-
発生早期(幼齢幼虫が見つかったら)
-
速効かつ摂食停止が速い薬剤を選ぶ:クロラントラニリプロール(プレバソン)を第一回散布(例:ラベルで示された希釈倍率:てんさいでは4000〜5000倍等)で成長阻止。
-
-
必要なら7–14日後(発生継続・第2回目)
-
別作用機構を使う(抵抗性回避):スピネトラム(ディアナSC)やフルベンジアミド(フェニックス)等を用いる。
-
-
予防・残効を長くしたい時/出芽期が続く地域
-
若齢幼虫に対してIGR(ルフェヌロン=マッチやフルフェノクスロン=カスケード)を組み入れ、次世代の発生を抑える(例:マッチ 3000倍 等)。
-
-
ローテーション指針(簡潔)
-
作用機構を混ぜない(同一IRACグループを立て続けに使わない)。例:28(クロラントラニリプロール)→5(スピノサン系)→15(IGR) の順など。IRACの推奨に従って回転すること。
-
まとめ
シロオビノメイガは、ホウレンソウやウリ類で秋にかけて被害が大きくなる後期発生型害虫です。初期の食害は目立たないものの、放置すると短期間で葉が壊滅的に食い荒らされるため、早期発見と初期防除がカギとなります。
圃場の雑草管理や防虫ネットの活用とあわせて、発生状況をよく観察し、適期に薬剤を散布することで被害を抑えることが可能です。
抑えるところは抑えて、
美味しい作物を作りましょう!
参考(主要出典)
-
プレバソンフロアブル5(製品情報/ラベル) — FMC / メーカー資料。てんさい・シロオビノメイガの適用記載。fmc-japan.com+1
-
日曹フェニックス顆粒水和剤(MAFF 登録情報/メーカー) — フルベンジアミドの適用表。てんさいへの適用追加情報等。農薬登録情報提供システム日本ソーダ
-
ディアナSC(スピネトラム)登録・適用表(MAFF/メーカー)。てんさい適用あり。農薬登録情報提供システムグリーンジャパン
-
カスケード(フルフェノクスロン)MAFFラベル/BASF資料(てんさい登録)。農薬登録情報提供システムBASF農薬
-
マッチ乳剤(ルフェヌロン)MAFF適用表(てんさい・シロオビノメイガの希釈・PHI等)。農薬登録情報提供システム
-
IRAC(作用機構分類・耐性管理ガイドライン)。Insecticide Resistance Action Committee+1
-
北海道病害虫防除所 等の注意報・地域情報(シロオビノメイガ早期飛来の報告/IGR活用の有効性事例)。agri.hro.or.jp北海道庁