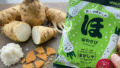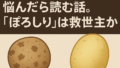長ネギが太らない…その肥料、間違ってませんか?
あると嬉しい薬味の代表格の長ネギ。
薬味など脇役ではもちろん大活躍だし、
意外に主役を張れる野菜!
そんな長ネギを失敗せずに作ってみたいですよね?
どうもチーパパです。
今回はそんな長ネギについて解説!
長ネギは、栽培期間が長くて管理も手間がかかるけど、
コツさえつかめば一年中収穫できる頼もしい野菜。(ハウスとかあれば)
この記事では、農業試験場の研究データをもとに、栽培方法・施肥設計・病気対策・家庭菜園でのポイントをまとめました。
手間がかかる分、失敗は避けたいですよね。
作付けを考えている方は是非チェック!!
読む前に急ぎで知りたい!!って言う方はとりあえずコレ!
ネギの栽培方法と作型
ネギは夏や秋にあるイメージですが、
「春まき・夏まき・秋まき・冬まき」に分けられ、
地域や気候によって作型が変わります。
露地だけでなくハウス栽培も多く、ほぼ周年生産が可能です。
最高ですね!
| 作型 | 播種時期 | 収穫時期 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 春まき夏どり | 1~5月 | 8~9月 | 生育後半が高温、急生長期に注意 |
| 春まき秋冬どり | 2~4月 | 10~12月 | 最も一般的、収量が多い |
| 秋まき夏どり | 8~10月 | 翌年6~7月 | 吸収量が多く、分施が重要 |
| ハウス栽培 | 通年 | 通年 | 高密植で軟白管理、液肥追肥が中心 |
ネギの施肥設計と栄養吸収のポイント
基本の施肥量(10aあたり目安)
- 元肥:
- 窒素 10~12kg
- リン酸 20~25kg
- カリ 10~12kg
- 追肥:
- 窒素・カリ 各10~15kgを3~4回に分けて
春まき夏どり:窒素吸収量 約13.5kg/収量3,000kg
春まき秋冬どり:窒素吸収量 約15.3kg/収量5,000kg
これが長年の研究で分かった、長ネギの必要成分。
秋どりタイプは9~10月に吸収がピーク。生育初期は控えめに、中期からしっかり肥料が効くように肥料設計を。
つまり、後半に効く緩効性肥料や分施設計がカギ。
ケース1:家庭菜園の場合 15㎡(5m×3m)
10a(1000㎡)→15㎡は 1/66.7 の面積。
元肥換算(15㎡あたり)
| 成分 | 10a基準 | 15㎡での使用量 |
|---|---|---|
| 窒素 | 10~12kg | 約0.15~0.18kg(150~180g) |
| リン酸 | 20~25kg | 約0.30~0.38kg(300~380g) |
| カリ | 10~12kg | 約0.15~0.18kg(150~180g) |
- 畑15㎡なら、コップ1杯分くらい(150~180g)ずつが元肥の目安。
追肥換算(15㎡あたり)
窒素・カリ 各10~15kg → 約0.15~0.23kg(150~230g)を3~4回に分けて。
つまり、1回あたり 40~70g前後。
- 畑15㎡なら、コップ1杯の半分くらい(70~90g)ずつ
が追肥の目安。
それを3~4回追肥する感じ。
ケース2:プランターの場合 (50cm × 30cm = 1500cm² = 0.15㎡)
10a(1000㎡)→0.15㎡は 1/6666.7 の面積。
元肥換算(プランター1個あたり)
| 成分 | 10a基準 | 0.15㎡での使用量 |
|---|---|---|
| 窒素 | 10~12kg | 約1.5~1.8g |
| リン酸 | 20~25kg | 約3.0~3.8g |
| カリ | 10~12kg | 約1.5~1.8g |
- プランターなら、ティースプーン1杯程度(1~2g)で十分。
追肥換算(プランター1個あたり)
窒素・カリ 各10~15kg → 約1.5~2.3g を3~4回に分ける。
つまり、1回あたり 0.5g前後。
- プランターなら、ティースプーン半分程度(0.5〜1g)で十分。
各要素の吸収特性
ネギがよく吸う栄養素は以下の順。
カリ>窒素>カルシウム>リン酸・マグネシウム
カリと窒素は生育中期に急増するため、このタイミングで追肥が必要。
特にカリが足りないと、葉が折れたり白根の伸びが悪くなります。
やっぱり追肥はNKがオススメ!
施肥の具体的なやり方(プロ農家)
- 苦土石灰200kg/10a、ようりん75kg/10aを全面散布
→pHとリン酸の調整をしましょう! - 深耕・砕土して、深さ15~20cmの植え溝を掘る
→深くしないと白い部分がすくなってしまう! - 化成肥料は根が直接触れないように施す
→肥料やけ防止! - 追肥は3~4回、生育に合わせて土寄せと同時に行う
→それをする事で生育アップ!
ネギの代表的な病気と防除のコツ
| 病名 | 症状 | 対策 |
|---|---|---|
| べと病 | 葉に灰白色の斑点。湿気で拡大 | 風通し確保・耐病性品種・殺菌剤散布 |
| さび病 | 赤褐色の斑点が葉に発生 | 高温多湿時に注意、早めの薬剤処理 |
| 白絹病 | 根元が白くカビ状に腐る | 連作回避、土壌消毒、石灰散布 |
| 黒腐病 | 葉鞘が黒く腐る | 排水性改善・雨除けハウスで予防 |
特に家庭菜園では、連作障害・過湿・風通しの悪さがトラブルの原因になります。
ネギは病気にも弱いですが、「環境」にも弱いので、土づくりと排水対策が一番の防除。
家庭菜園でのポイント
- 日当たりが良く、水はけのいい場所を選ぶ
- 苗を植える溝は「深めに(15cm以上)」掘る
- 土寄せを繰り返して白い部分(軟白部)を長く育てる(せっかくなら)
- 乾燥したらこまめに水やり
- 追肥量は少なめ・回数多めで調整
初心者なら「春まき秋冬どり」がおすすめ。
気温が安定していて管理しやすく、収穫量も多いです。
土寄せいらずの一本ネギ栽培で作業が激減!
ネギづくりで一番面倒な作業といえば「土寄せ」。。。
生育に合わせて7〜8回も行うのが普通で、腰も心も折れる重労働です。しかも、ネギの首元を土で埋めないように気を使うため、時間と集中力も奪われます。
ところが、土寄せいらずの栽培方法も存在します。
その常識をくつがえす方法は、
ウネに直径3cm・深さ35cmほどの穴を開け、そこへ苗を落とすだけ。
土はかけません。そのままでも根がしっかり張り、白根部が自然に伸びていくのです。
この方法なら、育てている間も土寄せの手間がゼロ。
しかも、保温や保湿効果も高く、夏場でも水やりいらず。
収穫時も根が浅いので、女性でも片手でスッと抜けます。
まさに待つネギづくり。
(この場合は追肥をしないから緩効性肥料がオススメ)
まとめ

長ネギは、選ぶ肥料によって栽培管理が変わる作物です!
生育後半の栄養補給と水管理を意識するだけで、ぐっと品質が上がりますよっ!
みんなで美味しい作物を作りましょう!
参考文献
●赤松富仁(2010)「松っちゃんのカメラ訪問記(169)やっぱり目からウロコ、土寄せいらずの一本ネギ栽培」『現代農業』2010年4月号、pp.11–15、日本農業新聞社。
●加賀屋博行(秋田県農業試験場):
「作型・栽培方法と施肥設計」『技術大系 ネギ 基礎編-圃場の準備-圃場の準備と施肥』、野菜編、専門館・農業総合、p.3