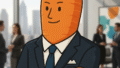新作「ほがじゃ(山わさび味)」もう食べた?ツーンの正体に迫るし、畑の姿も衝撃!
久々の当たりお菓子。
北海道の魅力が詰まったスナック「ほがじゃ 山わさび味」。
ふらっと立ち寄った道の駅で買った商品。
思わず食べた瞬間に
「旨ぁっ!」
意味もなくパッケージを見てしまった。
(パッケージのデザイン好き)

(表)

(中身)
ほがじゃという名のお菓子は、ほたて味を中心としたラインナップで、
北海道のお土産の定番になりつつある。
ポテチ同様、色々なフレーバーに挑戦しており、
私チーパパも見かけた時にちょっかいをかけているお菓子だ。
今回の「ほがじゃ 山わさび味」、
ただの地域限定ポテトスナックと思うなかれ。
袋を開けた瞬間、鼻を突くツンとした刺激が走る。これは人工的なわさびフレーバーじゃなくて、ワサビダイコン(山わさび)由来のアリルカラシ油の仕業だ。
山わさび=ワサビダイコンってどんな野菜?
そもそも山わさびって?
山わさび(ワサビダイコン)は、アブラナ科の多年草。
原産はフィンランドで、明治初期にアメリカ経由で日本へ入ってきたらしい。
当時はあまり普及しなかったけど、(日本ワサビが強すぎたんでしょ、、)
根茎の持つ独特の辛味と香りが注目され、今では粉わさびや漬物、そしてこうしたスナック菓子の香辛料として使われている。
● 辛味の正体はアリルカラシ油。
根茎に含まれる辛味成分は、
- アリルカラシ油
普段辛くはないが、
切ったり,すったり,細胞を壊すことで、酵素反応が始まり、
辛味成分(アリルカラシ油)が生成され、
これらが揮発して、あの“鼻を抜ける刺激”になる。
ちなみに、寒冷地ほど辛味が強くなるらしい。
だからこそ、北海道で山わさびが生産されている。
栽培の現場から見た「山わさび」
ワサビダイコンは根の分布が広く、半径1〜1.5m、深さ2mにもなる。
肥沃で深い土壌が必要で、pH5.5〜6.5くらいが最適。
寒地では11月収穫が一般的で、冷涼な環境でじっくり辛味を蓄える。
寒い地域で生まれる刺激は、気候ストレスによる植物の防御反応でもある。
だからこの辛味には、「生き抜く力」が詰まってるとも言える。
又、栽培されている山わさびの姿が衝撃。

※遠くてすいません。
でかいなっ。
さとうだいこんに似ている。
肥料成分と土壌管理
自然に生えているものもあるので、それを増やしたい、
又は栽培したい方向けに、、、
| 項目 | 必要性・目安 |
|---|---|
| 窒素(N) | 適度(多すぎると葉茂りして根肥大が悪化) |
| リン酸(P) | 根の発達と辛味成分形成に重要。基肥で十分に。 |
| カリ(K) | 根の肥大促進・貯蔵性向上に必要。追肥でも補う。 |
| 苦土・石灰 | pH6.0〜6.5程度が理想。酸性を嫌う。 |
| 有機質肥料 | 堆肥や完熟有機物で地力維持。排水性も改善。 |
→ おおむね「リン酸>カリ>窒素」のバランスが望ましい。
過剰施肥は辛味成分の低下や病害の発生を招く。
実食レビュー:ツンとくるけど、クセになる。
「ほがじゃ 山わさび味」は、澱粉ベースのサクサク生地に、山わさびの刺激がしっかり乗ってる。
最初の一枚でツン、二枚目でハマる。
刺激がありながら後味は軽く、油っぽさが少ないのが印象的。
割った状態で入っているので、辛いパウダー?が感じやすい仕様。
辛味の立ち上がり方が自然で、人工香料の「ツン」とは違う深みがある。
もう食べたら辛くて何もしたくない、とかいうレベルではなくて、
いわゆる辛旨!!
まとめ
ストレス大事。。
- 山わさび=ワサビダイコンはアブラナ科の多年草
- 辛味成分はカラシ油類。寒冷地ほど辛味が増す
- 根は深く伸びるため、肥沃で排水の良い土壌が大事
- 「ほがじゃ 山わさび味」は、その特性を活かした“北海道が臭うスナック”
食べ終えたあと、鼻の奥に残るツンとした余韻がなんか癖になる。
もし自家栽培するなら、、、
もし自家栽培で「山わさび」を試すなら、
- 冷涼地向け(夏の高温は苦手)
- 深く耕した畑
- pH6前後、やや湿り気のある土
- 春植え・晩秋収穫がベスト
…といった条件を押さえるといい。
ごはんにかけると美味しいですよね。
醤油漬けもいい。
あまり作る方いないかっ。
美味しい作物を食べていきましょう!
参考資料
『野菜編 第11巻 特産野菜(1988)』馬場英実著・長野県野菜花き試験場
データ:ワサビダイコンの形態・栽培技術・辛味成分