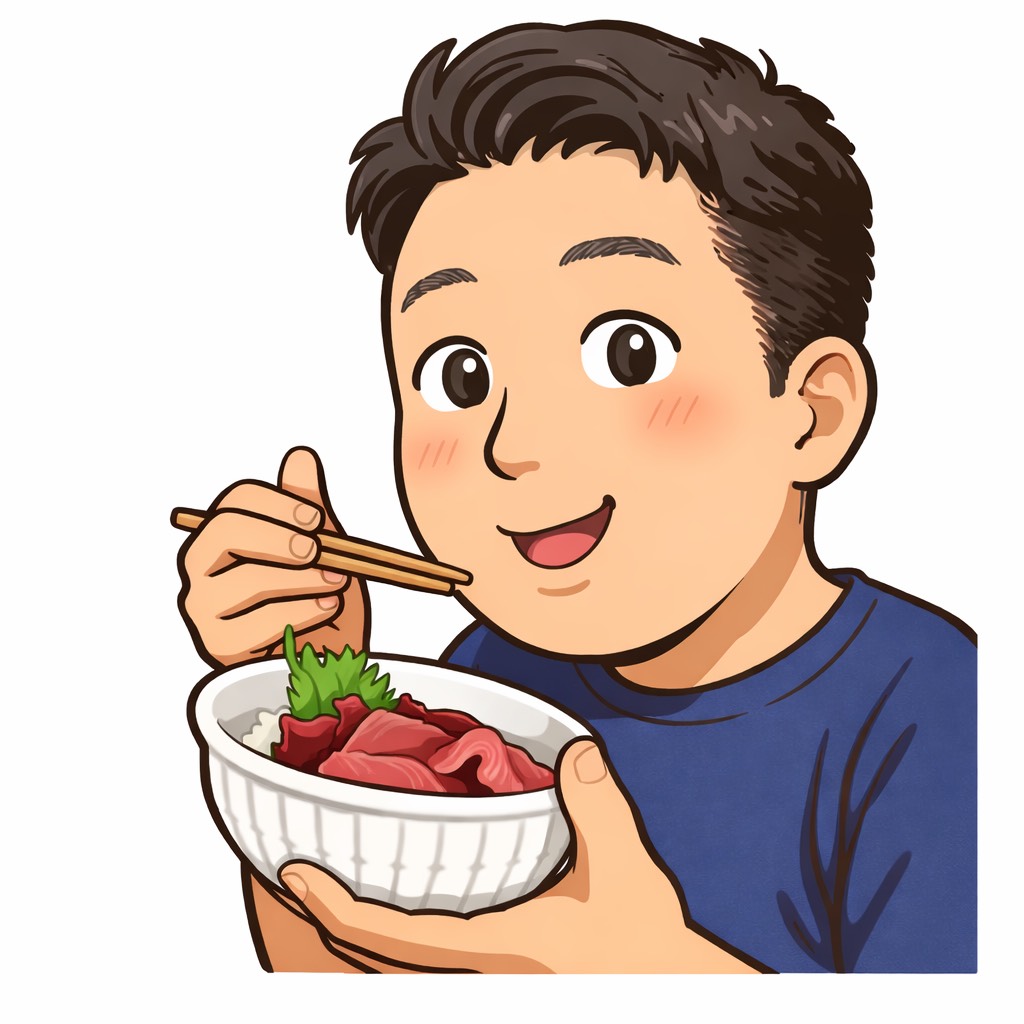男爵薯(だんしゃくいも)の特徴と栽培ポイント|家庭菜園初心者にもおすすめの定番品種
男爵薯とは?

男爵薯(だんしゃくいも)は、日本で最も有名なジャガイモ品種のひとつ。北海道を中心に栽培され、スーパーや家庭料理で幅広く使われています。
男爵薯の歴史|北海道七飯町が発祥
男爵薯は、明治41年(1908年)に川田龍吉男爵がイギリスから輸入した種いもを、北海道七飯町の農家が試作したことから広まりました。評判がよく一気に地域に普及し、「男爵薯」と呼ばれるようになります。
現在も七飯町は「男爵いも発祥の地」として知られ、道の駅なないろ・ななえでは男爵いもを使ったコロッケやソフトクリームが人気を集めています。
【公式】道の駅なないろ・ななえ
丸みを帯びたごつごつした形が特徴で、粉質(ホクホク系)の食感はコロッケやポテトサラダ、マッシュポテトにぴったりです。
家庭菜園でも人気が高く、初心者が最初に挑戦する品種としておすすめされる定番ジャガイモです。
男爵薯の品種特性
収量や育てやすさ
- 収量は中程度で安定しやすい
- 発芽が良く、育てやすい
- 初心者でも比較的失敗が少ない
植え付けから収穫まで約100〜110日と生育期間はやや長めです。プランターより畑での栽培に向いています。
病害虫への強さ・弱さ
男爵薯は育てやすい一方で、病害虫に対する抵抗性は低めです。以下の点に注意が必要です。
- ジャガイモシストセンチュウに弱い
抵抗性を持たないため、発生圃場で作ると被害を受けやすく、収量が落ち、土中の線虫も増えてしまいます。 - ネグサレ線虫には比較的強い
一部の線虫には耐性があり、この点は安心材料。 - 疫病に弱い
「メークイン」「キタアカリ」と同様に、疫病抵抗性の遺伝子を持たず、圃場抵抗性も弱いです。葉だけでなく、塊茎腐敗も多く発生します。 - ウイルス病にかかりやすい
PVX(Xモザイク)、PVY(Yモザイク)に弱く、特に開花期以前に感染すると落葉やえそ症状が出ることがあります。 アブラムシが媒介するやつ。 - そうか病に極めて弱い
粉状そうか病に関しては既存品種の中で最も弱いレベル。「農林1号」よりも弱いとされ、家庭菜園では土壌pHや連作に要注意です。 - 生理障害が出やすい
男爵薯は大イモに中心空洞が出やすく、褐色心腐の発生も他品種よりやや多め。早掘りでは水浸状になり、収穫が遅れると内部に褐色斑点が生じやすいです。
まとめると、「育てやすいけど病害虫には弱い品種」。初心者が栽培する場合は、
-
正規の種イモを使う
-
連作を避ける
-
土寄せと排水管理を徹底する
-
必要に応じて防除剤を活用する
といった基本対策で失敗を減らせます。
まじめにやると以外に栽培するのが大変。。。
味や食感
- ホクホクとした粉質の食感
- 甘みよりも粉のうまみが強い
- 煮崩れしやすく、煮込みには不向き
じゃがバターやコロッケで食べると、男爵薯ならではのホクホク感を存分に楽しめます。
向いている料理
- コロッケ
- ポテトサラダ
- じゃがバター
- マッシュポテト
- ポタージュスープ
粉質を活かせる料理と相性抜群です。
男爵薯の栽培方法と注意点
発芽・植え付け
- 芽が多すぎる種イモは、芽の位置を見て2〜3片に切る
- 植え付け時期は春(3〜4月)か秋(8月下旬〜9月)
- 植え付け前に日光に当てて「芽出し」しておくと発芽がスムーズ
追肥と管理
- 芽が10cm程度に伸びたら1回目の土寄せ
- 花が咲く前後に追肥と2回目の土寄せを行う
- 塊茎肥大期にしっかり水分を与えると収量安定
収穫時期
- 茎葉が黄色く枯れてきたら収穫のサイン
- 掘り上げ後は日陰で乾燥させ、土を落として保存
家庭菜園初心者におすすめできる理由
- 発芽が安定して育てやすい
- 味の知名度が高く、料理に幅広く使える
- 種イモがホームセンターやネット通販で入手しやすい
ただし病害虫に弱いので、初めて育てるなら防除と土壌管理を意識するのがおすすめです。
保存方法のコツ
男爵薯は芽が出やすいので保存環境に注意が必要です。
- 直射日光を避け、10℃前後の涼しい場所で保存
- 光に当てると緑化し、有害なソラニンができるため注意
- 新聞紙に包んでネットやかごに入れて通気性を確保する
種イモの購入方法
男爵薯の種イモは、以下で手軽に購入できます。
- ホームセンター(春先から販売)
- JA直売所
- ネット通販
ネット通販なら有機栽培用やサイズ違いの種イモも選べるので便利です。
まとめ
男爵薯は、日本のジャガイモの定番であり、家庭菜園でも大人気の品種です。
- ホクホク感を活かした料理に最適
- 育てやすいが病害虫に弱いため対策は必須
- 保存方法を守れば長期保存も可能
これからジャガイモ栽培を始めたい人は、まず男爵薯から挑戦してみましょう!
やっぱり美味しいですしね!